類稀なる才能、深い信頼で結ばれた二人が紡ぐ至高の音楽
庄司紗矢香&ジャンルカ・カシオーリ デュオ・リサイタル
- 室内楽
- 日時
- 2026年3月6日(金) 19:00
- 開場 / 終演予定
- 18:20 /
ピックアップ
関連ニュース
- 2026/1/22 庄司紗矢香に聞く!ジャンルカ・カシオーリと巡る “霧に包まれたような 遠い昔を振り返る” プログラム
- 2025/12/22 【掲載情報】庄司紗矢香&ジャンルカ・カシオーリ デュオ・リサイタル (3月6日 サントリーホール)
- 2025/12/9 【2025年12月】ジャパン・アーツぴあオンラインチケット発売情報
- 2025/10/14 【2025年10月】ジャパン・アーツぴあオンラインチケット発売情報
- 2025/10/7 【掲載情報】庄司紗矢香(2025年9月~10月)
- 2025/7/24 【掲載情報】ラハフ・シャニ指揮 ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団 (6月23日 ミューザ川崎シンフォニーホール、6月26日・27日 サントリーホール、6月28日 横浜みなとみらいホール)
- 2025/7/15 【2025年7月】ジャパン・アーツぴあオンラインチケット発売情報
- 2025/6/27 【速報】庄司紗矢香&ジャンルカ・カシオーリ デュオ・リサイタル 2026年3月公演開催決定!
- 2025/4/17 庄司紗矢香が韓国でモーツァルトを熱演!
- 2025/4/16 【海外公演レポート】ラハフ・シャニ指揮ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団 アムステルダム公演
チケット詳細Ticket Information
チケット発売情報
- ① 10月18日(土) 10:00a.m.~発売 ジャパン・アーツぴあオンラインチケット WEB
- ② 10月25日(土) 10:00a.m.~発売 一般 TELWEB
- WEB … インターネットで購入可
- TEL … ジャパン・アーツぴあコールセンター 0570-00-1212
※先行発売などで満席になった席種は、以降販売されない場合がございます。
チケット残席状況
残席あり / × 売り切れ
2026/3/6
一般
通常価格
- SS席
- –
- S席
8,500円
- A席
7,500円
- B席
6,500円
- C席
5,500円
- D席
- –
- E席
- –
- 学生席
- –
- 全席指定
- –
学生割引
通常価格
- SS席
- –
- S席
4,300円
- A席
3,800円
- B席
3,300円
- C席
2,800円
- D席
- –
- E席
- –
- 学生席
- –
- 全席指定
- –
- ◎学生割引
- *残席がある場合に限り、1/16(金)10:00より受付を開始いたします。
- *社会人学生を除く25歳までの学生が対象です。公演当日、入口または窓口にて学生証を拝見いたします。
(学生証がない場合は一般料金との差額を頂戴いたします。)
特別割引
- ◎シニア・チケット=65歳以上の方はシニア料金でお求めいただけます。
S席¥7,700 - ◎車椅子の方は、本人と付き添いの方1名までが割引になります。(ジャパン・アーツぴあコールセンターでのみ受付)
その他プレイガイド
- サントリーホールチケットセンター suntory.jp/HALL 0570-55-0017
- チケットぴあ t.pia.jp [Pコード 310-260]
- イープラス eplus.jp
- ローソンチケット l-tike.com [Lコード 31006]
チケット購入にあたっての注意事項
曲目・演目Program
- モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第24番 ヘ長調 K. 376
- ブラームス、ディートリッヒ、シューマン:F.A.E ソナタ
- ダラピッコラ:タルティニアーナ第2番
- ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ 第1番 Op.78「雨の歌」
公演によせてMessage
自由、されど根拠をもって
庄司紗矢香にとって、2009年のジャンルカ・カシオーリとの初共演は、大きな転換点だったという。
たとえばモーツァルトのヴァイオリン・ソナタをひくときに、庄司が子供のころから教わってきた、さまざまな規則やタブーといった「枠」。その「枠」にしばられることに窮屈さを感じ、もっと自由な表現を内心では求めていた庄司の、よりオーガニックで人間的な演奏を実現する夢をかなえてくれたのが、カシオーリとの共演だった。それはけっして自分勝手なものではなく、モーツァルトと同時代の18世紀のヴァイオリン教本などの記述に基づいている。つまり、地に足のついた自由、根拠のある独創なのだ。
初共演から15年を超え、「こんなに長くコラボレーションが続くとは、夢にも思わなかった」と庄司は笑っていたが、レパートリーは多彩さを増し、表現はさらに情感を深め、息のあったものとなっている。
2022年の公演では、カシオーリのひくフォルテピアノとともに、天翔るようなイマジネーションと繊細さを共存させた、素晴らしい演奏を聴かせてくれた。とりわけ「クロイツェル・ソナタ」の創意と意欲にみちた名演は忘れがたい。
今回は現代のピアノを用いて、18世紀から20世紀にかけての、さまざまな時代の作品を聴かせてくれる。全曲録音を継続中のモーツァルトのヴァイオリン・ソナタからの第24番K. 376に始まり、次に名ヴァイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムのモットー「自由、されど孤独(Frei aber einsam)」の頭文字による3つの音をモチーフに、友人のブラームス、ディートリッヒ、シューマンの3人が共作した、F.A.E ソナタ。ブラームス作曲のスケルツォ楽章が有名だが、他の楽章は演奏機会が少ないだけに、ここでその真価を知ることができるだろう。
続いて18世紀のタルティーニの旋律をモチーフにした、20世紀のダラピッコラによるタルティニアーナ第2番。18世紀と20世紀の音楽が時空を超えて出会う、庄司とカシオーリのスタイルにぴったりの作品だ。そしておしまいにブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」。この名曲にもどんな新しい生命が吹き込まれるのか、とても楽しみだ。
音楽評論家 山崎浩太郎
全国公演日程National performance
プロフィールProfile
庄司紗矢香 Sayaka Shoji (ヴァイオリン, Violin)

唯一無二の芸術的多様性とレパートリーへの緻密なアプローチで、国際的に認められるヴァイオリニスト。その音楽的言語に対する非凡な洞察力は、これまで拠点を持ってきたヨーロッパと日本、二つの背景の混合に由来する。
東京に生まれ、3歳でイタリアのシエナに移住。キジアーナ音楽院とケルン音楽大学で学び、14歳でルツェルン音楽祭にて、ルドルフ・バウムガルトナー指揮ルツェルン祝祭管弦楽団との共演でヨーロッパ・デビュー、及びウィーン楽友協会に出演した。
1999年、パガニーニ国際コンクールにて史上最年少優勝。以来、ズービン・メータ、ロリン・マゼール、セミョン・ビシュコフ、マリス・ヤンソンス、ユーリ・テミルカーノフなど多数の一流指揮者と、イスラエル・フィル、フィルハーモニア管、クリーヴランド管、ロンドン響、ベルリン・フィル、ロサンゼルス・フィル、ニューヨーク・フィル、聖チェチーリア国立アカデミー管、チェコ・フィル、マリインスキー管、NHK響など共演多数。室内楽では、ジャンルカ・カシオーリとの15年にわたる共演のほか、多くのアーティストと積極的に共演を重ねるほか、多様な芸術分野とのコラボレーションでも世界的に高く評価されている。
これまでドイツ・グラモフォンから、テミルカーノフ指揮サンクトペテルブルク・フィルとの録音や、メナヘム・プレスラーとのリサイタル・アルバムなど多数リリース。2022年と2025年には、ジャンルカ・カシオーリとのモーツァルト:ヴァイオリン・ソナタのアルバムをリリースした。
2016年、芸術分野で顕著な影響を及ぼした者に与えられる「毎日芸術賞」を受賞。2012年日経ビジネスの「次世代を創る100人」に選出。2025年第37回ミュージック・ペンクラブ音楽賞受賞。
使用楽器は上野製薬株式会社より貸与されているストラディヴァリウス「レカミエ」1729年製。
- 庄司紗矢香オフィシャルウェブサイト
- https://sayakashoji.com/
ジャンルカ・カシオーリ Gianluca Cascioli (ピアノ, Piano)
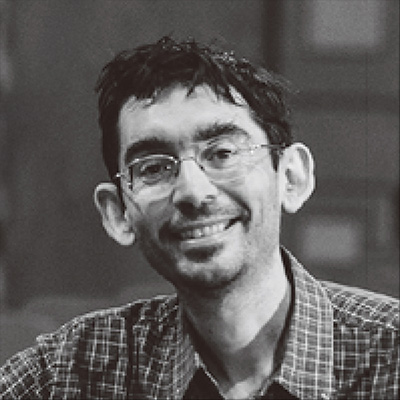
1979年イタリアのトリノ生まれ。ピアノをイモラのピアノ・アカデミーでフランコ・スカラ(カルロ・ゼッキの教え子)に師事。94年ルチアーノ・ベリオ、エリオット・カーター、マウリツィオ・ポリーニ、チャールズ・ローゼンが審査員を務めたウンベルト・ミケーリ国際ピアノ・コンクールで優勝し、国際的な注目を集めた。
以来ヨーロッパ、北米、日本の主要な音楽都市に演奏の場を広げている。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ボストン交響楽団、シカゴ交響楽団、ニューヨーク・フィルハーモニック、ロスアンゼルス・フィル、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団など著名なオーケストラと、クラウディオ・アバド、ウラディミール・アシュケナージ、チョン・ミョンフン、ダニエル・ハーディング、リッカルド・ムーティ、ロリン・マゼール、ズービン・メータ、ユーリ・テミルカーノフなど名だたる指揮者との共演は数えきれない。また、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ、ユーリ・バシュメット、マキシム・ヴェンゲーロフ、フランク・ペーター・ツィマーマン、クレメンス・ハーゲン、ザビーネ・マイヤー、アルバンベルク弦楽四重奏団などとも共演。
録音活動も積極的に行っており、ドイツ・グラモフォン、デッカ、ノヴァリス、アルモニア・ムンディといったレーベルから数々の作品を発表。庄司紗矢香とはモーツァルトのヴァイオリン・ソナタ(ピリオド楽器による/DGG)などをリリース。
カシオーリは、作曲をトリノのジュゼッペ・ヴェルディ音楽院でアレッサンドロ・ルオ・ルイおよびアルベルト・コッラに師事。彼の作品は、いくつかの作曲コンクールで優勝し、重要な会場で演奏されている。
主催・協賛
- 主催
- ジャパン・アーツ
- 協力
- ナクソス・ジャパン


