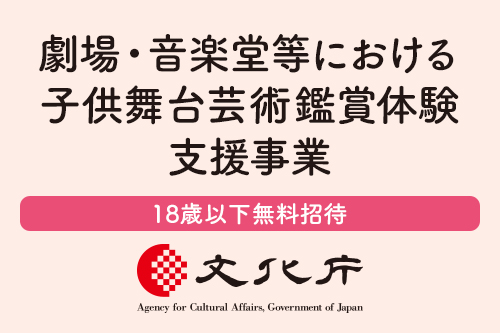2025/6/26
ニュース
バイエルン国立管弦楽団~はじまりは「オーケストラ」
「歌劇場オーケストラ」の本質を体現するバイエルン国立管弦楽団が9月に来日します。このオーケストラは、宮廷オーケストラを起源に持つ特別な存在。その歩みをたどる長木誠司氏のエッセイを、ぜひご一読ください。
長木誠司(音楽学・音楽評論家)
専属オーケストラを持つ歌劇場という文化を持たない日本では、演奏会場(コンサートホール)と歌劇場という区別が、長年にわたってなかなか定着しなかった。よこすか芸術劇場のように馬蹄形の座席を持つオペラ仕様の劇場や、続く新国立劇場、あるいはびわ湖ホール、今世紀になってからは松本市民芸術館といった、オペラ専用の(とはいえ、上演頻度はヨーロッパの大劇場にはるかに及ばない)空間が誕生した1990年以来、オペラは演奏会場とは異なった空間で本来上演されるべきものだという感覚が日本の聴衆の間にも生じてきた。それまで、「無目的」と揶揄されることも多かった多目的ホールばかりの日本には、「演奏会文化」と「オペラ文化」の違い、もっと言えば、両者の聴衆の性格や会場での振る舞いの違いが分かりにくかったと言える(今でも聴衆の違いは分かりにくいかも知れない)。
ウィーン宮廷歌劇場のオーケストラが、オペラとは別途に演奏会を始めたことから成立したウィーン・フィルに代表されるように、ヨーロッパの近代的なオーケストラの誕生には、もともと歌劇場のピットに入っていた団体の存在が重要だ。ベルリン・フィルのように当初から演奏会専用のオーケストラが設立されて定期的に公開演奏を行うというのは、それほど古い歴史を持つ話ではなく、ヨーロッパの市民社会がオペラのほかに、娯楽としての演奏会を必要とし始めた19世紀半ば以降のことに過ぎないし、20世紀になって放送局が自前のオーケストラを持つようになってからこうしたオーケストラは増えていった。歌劇場の歴史はもっと古く、ヨーロッパの各地に宮廷があったころまで遡る。
現在でも、ヨーロッパの歌劇場の座付きオーケストラは、オペラ公演とは別に、オーケストラ公演を、市内の別の会場で定期的に開催するところが多い。例えば、ドイツの地方都市などではたいていそうなっている。だから、ミュンヒェンのバイエルン国立管弦楽団(バイエルン・シュターツオーケストラ)も、歌劇場のオーケストラが演奏会も行うようになったのだ、と通ぶって考えると、ちょっと違う。
ドイツ国内では、ベルリン国立歌劇場のオーケストラであるベルリン・シュターツカペレなどとも共通するのだが、ミュンヒェンの場合、まず宮廷オーケストラがあった。もともとは宮廷附属の教会で主として宗教曲を合唱とともに演奏する団体として16世紀初頭に設立されたのだが、それが17世紀後半からさかんに上演されるようになったオペラの伴奏オーケストラとしても活動するようになったのが、バイエルン国立管弦楽団の初期の歴史となる。だから、この団体は当初から「オーケストラ」だったと言っても過言ではない。もちろん、独立した演奏会を営む団体ではなかったが、宮廷歌劇場から生まれたオーケストラだと考えるのは事実に即していない。
「はじまり」からオーケストラであったバイエルン国立管弦楽団は、それゆえオペラの伴奏団体というよりも「オーケストラ」としての自覚が強い。ベルリンでは3つの歌劇場のオーケストラはみな独立した定期演奏会を持っているが、ミュンヒェンでオペラとオーケストラの両方に定期的に出演するオーケストラはここだけだ。それゆえの自負というものも強く持っている。だから、例えばウィーン・フィルとともに晩年のカルロス・クライバーが信頼していたのもこのオーケストラだったし、ミュンヒェンの他の演奏会専門のオーケストラであるミュンヒェン・フィルやバイエルン放送交響楽団と比べても、優劣付けがたい演奏会を例年行ってきている。なかでも、シーズン中6回にわたって毎回2夜ずつ、本拠たるバイエルン国立歌劇場で行われる「アカデミー演奏会」は、室内楽演奏会とともに主要なもので、ことに先代のペトレンコやユロフスキが歌劇場のシェフになってからちらほら現代作品も入ってきて、並みの演奏会プロパーのオーケストラよりも多彩なプログラムが披露されるようになった。2025年秋からのシーズンにはペトレンコをはじめ、ヘラス=カサドやセバスティアン・ヴァイグレといった顔ぶれも登場する。
オペラのピットのなか、すなわち歌劇場でではなく、コンサートホールでこのオーケストラの姿を見て聴くことは、ミュンヒェン市内以外ではなかなか体験できない。今回の来日では、じっくりと彼・彼女らによる「オーケストラ」演奏を堪能しよう。